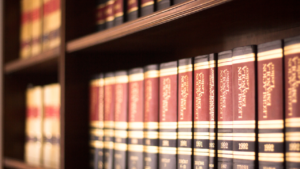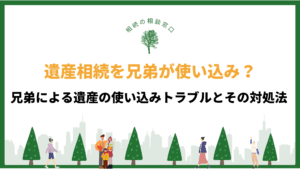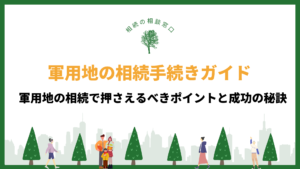いとこが亡くなった場合、いとこ同士は法定相続人に該当しないため、遺産を相続することはできません。 遺産を受け入れるためには、生前に遺言で遺贈を指定してもらうか、特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行う必要があります。本記事では、いとこの遺産相続に関する具体的な方法を専門家が詳しく解説します。
いとこは相続人に該当しない
いとこの遺産は原則として継承できない
悩みでは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続できる人を法定相続人として定めています。その順位は以下の通りです。
- 第1位:子や孫などの直系卑属
- 第2位:父母や祖父母などの直系尊属
- 第3位:兄弟姉妹
また、配偶者は常に相続人になります。
第1順位がいれば配偶者とともに相続人になり、不在の場合は第2順位と配偶者が相続人になります。第2順位も不在であれば、第3順位が配偶者とともに相続人となります。
このように、いとこは法定相続人の範囲に含まれていません。 そのため身寄りのないいとこがいたとしても、その遺産を相続することは原則できません。財産を相続できるわけではないのです。
身寄りのないいとこの財産は最終的に国庫へ
では、法定相続人がいない場合、その遺産はどうなっているのでしょうか。この場合、特別縁故者に該当する一定の人がいない場合は、遺産は最終的に国庫に帰属します。
特別縁故者とは、以下のような条件に該当する人をお伺いします。
- 被相続人と生計を共にしていた人
- 被相続人の療養看護に尽力した人
- その他、特別に相続された人とな縁があった人
かつて、いとこと同居していたり、生活資金を援助していたり、療養看護を行っていた場合は、特別縁故者として認められる可能性があります。
相続人がいない場合の遺産は、以下の手続きが取られます。
- 利害関係人または能力官の請求により、相続財産管理人が選ぶ
- 管理者が債権者や受領者への支払いを行う
- 相続人がいないことが確定すると、特別縁故者への分与が実施される
- 特別縁故者への分与後に残った財産がある場合は、国庫に帰属する
特別縁故者としての財産を考えるためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きについては、後ほど詳しく解説します。
いとこが遺産を相続するには遺言が必要
遺贈によるいとこの遺産の取得
いとこの遺産は、法定相続人がいない場合でも、何もしなくても相続することはできません。そのため、遺産を取得する方法として、被相続人に遺言を残してもらうことが重要です。遺言とは、亡くなった方が自身の財産の売却方法を最終的な意思として書面に記したものを言います。
遺言は「普通方式」と「特別方式」に分類され、一般的に利用されるのは普通方式の遺言です。
- 自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。手軽に作成できますが、法定要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしながら公証人に確認を依頼する形式です。
- 公正証書遺言:公証人が関与して作成する形式で、記載内容や形式の不備が避けられます。
遺言による遺贈には、以下の2種類があります。
- 特定遺贈:特定の財産を特定の人に譲る方法
- 包括遺贈:遺産全体の一定割合を譲る方法
自筆証書遺言より、公正証書遺言の方が安心
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、記載内容や形式の不備を防ぐ確実な方法です。そのため、いとこの遺産を取得する目的であれば、公正証書遺言を選ぶ方が安心です。自筆証書遺言の場合、不備があれば無効となり、結果的に遺産を受け取れなくなるリスクがあります。
なお、自筆証書遺言は原則として遺言者の死亡後に家庭裁判所の「検認」を経る必要がありますが、公正証書遺言では手続きが不要になるメリットもあります。
相続トラブル、遺産分割、遺言など
相続トラブルに関するご相談
5,500円/1h
050-6883-9809
受付時間:9:00~18:00
相続トラブル、遺産分割、遺言など
相続トラブルに関するご相談
5,500円/1h
050-6883-9809
受付時間:9:00~18:00
特別縁故者として認められるに
遺言がない場合、特別縁故者として認められれば、いとこの遺産を相続することが可能です。法定相続人がいない場合、相続財産管理人が財産の管理を行い、債権者への支払や特別縁故者への分与を行うことになります。相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することが最初の手続きです。選任の請求は利害関係者でも行えるため、特別縁故者に該当する人も行うことができます。
選任された相続財産管理人は、まず2か月以上の期間を定めて、権利者や受取人が請求を行うべき公告を行います。その後、権利があった権利者等に対し、遺産からの支払いを行います。一方相続人がいない場合は、6ヶ月以上の期間を定めて相続人を捜索する公告が行われ、期間満了後に相続人が存在しないことが確定します。
相続人が存在しないが確定した場合、家庭裁判所は、縁故者と認められた人に対して財産の分与を行うことができます。特別縁故者には、「被相続人の療養看護に配慮した」「その他被相続人と特別の縁故があった者」とされています。但し、特別縁故者として認められるための請求は、相続人調査の公告期間満了後3ヶ月以内に行う必要があります。なお、請求先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になり、申立書と申立人(財産分与の請求を行う人)の住民票などを添付して申し立てることになります。
相続税は2割加算となる
いとこの財産を相続する場合、特別縁故者として財産を受け取る方法は、手続きに最短でも1年ほどかかります。また、特別縁故者として認められない可能性もあるので、確実に遺産を取得したい場合、さらに、いとこが複数いる場合は、感情的なトラブルが発生する可能性があるため、事前に弁護士へ相談することを検討しましょう。
いとこは法定相続人ではないもの、基礎控除額を超える遺産を考える場合には相続税の申告が必要です。また、被相続人の相続人や一親等の血族以外が財産を相続する場合、相続税額に2割加算が適用されます。
 弁護士 御厨
弁護士 御厨いとこからの相続は、父と兄弟姉妹の場合と比べて複雑で、法律や税金の手続きが高くなります。スムーズな手続きのためには、弁護士、司法書士、税理士などの専門家への相談を早めてくださいにしましょう。
(※この記事の内容は2021年2月1日時点の情報に基づいています)