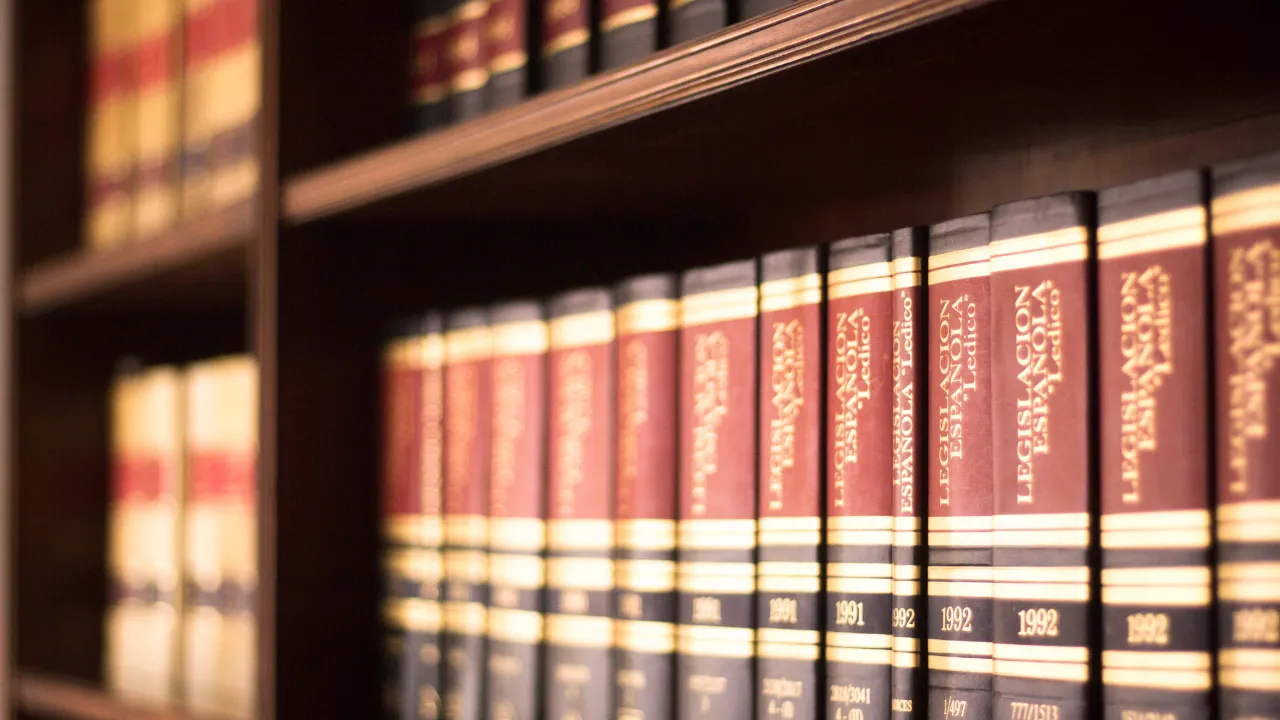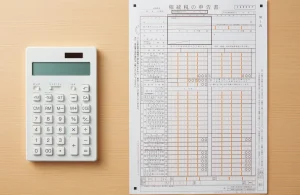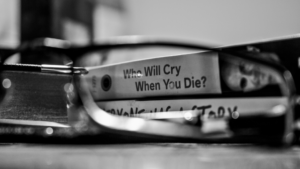【遺言の有効性】認知症の影響があったが、遺留分の主張が通った事例

クライアント情報
武蔵村山市在住60代 女性
問題となっていた事柄
依頼者の父が公正証書遺言を作成し、「全財産を長男に相続させる」との内容が記載されていたが、遺言作成当時、父は病院から認知症と診断されており、判断能力に疑問があった。
また、遺言作成の翌年、依頼者が父に遺言内容を確認したところ、「同意していないのに勝手にやられた」との発言があり、遺言の有効性に疑念を抱いた。
クライアントは、この遺言が無効になるのではないかと考え、弁護士に相談した。
争点
遺言の有効性
遺言作成時の被相続人の意思能力が十分であったかが争点。認知症の影響で判断能力が欠如していた場合、遺言は無効となる可能性がある。
遺留分の主張
仮に遺言が有効と判断された場合でも、依頼者には法律で保障された「遺留分」の請求権があるため、遺産の一部を取得できる可能性がある。
弁護士が介入した結果
公証役場での調査
まず、公証役場で遺言の内容を確認し、遺言によって依頼者の遺留分が侵害されていることを特定した。
医療記録の取得
被相続人の通院履歴や診断書を病院から開示請求し、遺言作成時の認知機能の状態を調査した。その結果、介護認定申請がなされており、「日課を理解できない状態」とされており、「ひどい物忘れ」の症状があると診断されていたことが判明。
裁判所での主張
遺言無効を主張:遺言作成当時、被相続人の認知症が進行しており、遺言内容を理解できる意思能力がなかった可能性を指摘。
遺留分請求:仮に遺言が有効と認められても、依頼者の遺留分が侵害されているため、遺産の一部を請求する権利があることを主張した。
裁判所の判断
医師の意見や証拠を基に、遺言作成当時の意思能力を慎重に検討する。軽度の認知症であったものの、遺言内容を理解し決定できる状態であったと判断された場合、遺言は有効と認められる可能性がある
実務的なポイント
遺言の有効性を確保するには?
遺言作成時に医師の診断書を取得する、信頼できる証人を立てることで、後の争いを防ぐことができる。
相続トラブルを避けるための対策
公正証書遺言を作成する際は、遺留分を考慮した内容にすることが重要であり、特定の相続人に偏った遺言を残す場合は、事前に遺留分減殺請求のリスクを弁護士と相談しておくべきである。
まとめ
今回のケースでは、被相続人が遺言を作成した当時の認知症の状態が争点となり、遺言の有効性が問われることとなった。
最終的に、裁判所は遺言の有効性を判断する一方で、遺留分の侵害が認められる場合は適正な代償金の支払いを命じた。
遺言をめぐる争いを防ぐためには、遺言作成時に意思能力の確認を徹底し、遺留分にも配慮することが重要である為、専門家に相談をすることが望ましい。