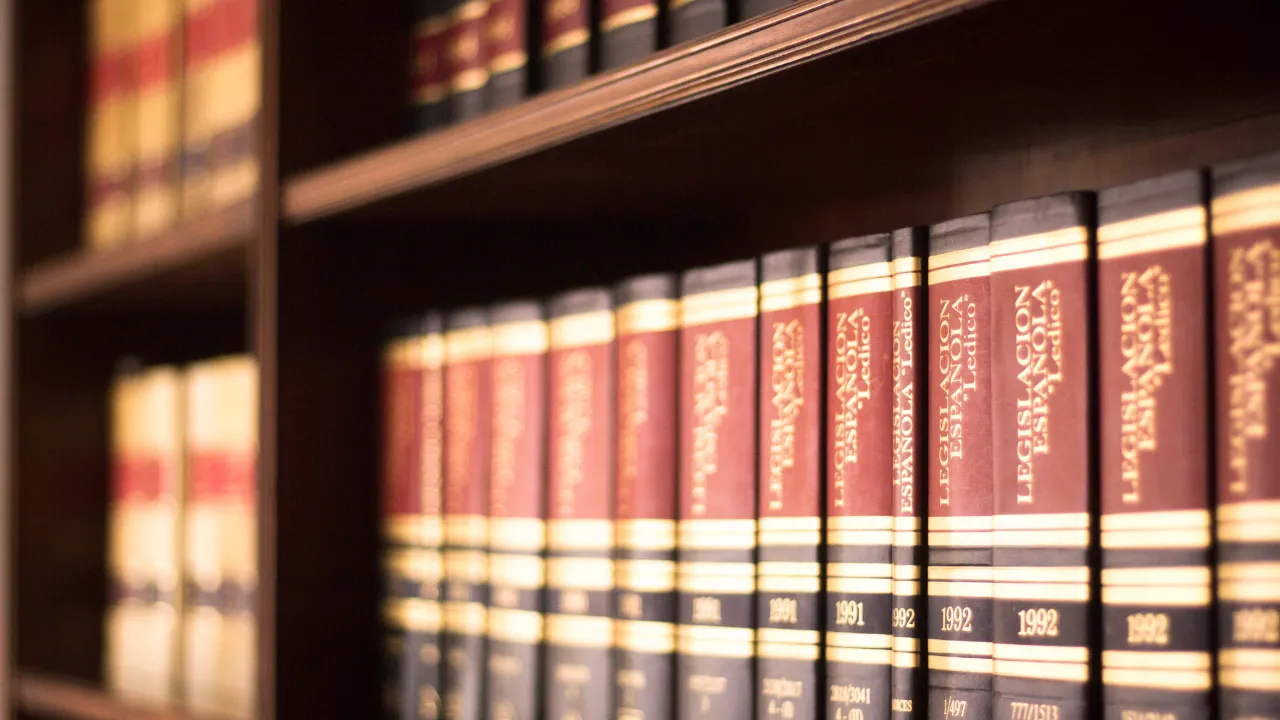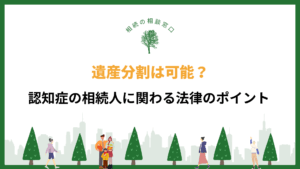子どものいない夫婦こそ遺言が大切な理由!~法定相続人の仕組み~

子どもがいない夫婦の相続・配偶者はすべて相続できるのか?
子どもがいない夫婦では、遺産がすべて配偶者に渡るとは限りません。たとえ配偶者がいても、被相続人の両親(または祖父母)、兄弟姉妹が存命であれば、彼らも相続人となる可能性があります。つまり、遺産は配偶者のみが受け取るとは限らないのです。
その結果、配偶者にとっては望まぬ相続人が現れる場合もあり、配偶者の家族と遺産を分け合う状況が生まれることもあります。
法定相続人と法定相続分の基本
民法では、誰が相続人になるか、どのくらいの割合で相続するかが定められており、これをそれぞれ「法定相続人」「法定相続分」といいます。遺言がなければ、これに基づいて相続が行われます。
配偶者とその他の相続人との関係
配偶者は常に相続人となりますが、その相続分は他の相続人の有無によって変わります。
| 相続人構成 | 配偶者の相続分 | その他の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子ども:1/2 |
| 配偶者と父母(祖父母) | 2/3 | 父母等:1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
| 配偶者のみ | 全部(10/10) | なし |
配偶者には、法律上の婚姻関係が必要であり、内縁関係や事実婚の場合は相続人とはなれません。また、別居中であっても離婚していなければ相続権があります。
元配偶者は相続人にはなれませんが、その間に生まれた子は法定相続人となります。連れ子には養子縁組がない限り相続権はありません。
血族相続人の順位と範囲
血族相続人には以下のような優先順位が設けられています。
| 順位 | 関係 | 代襲相続 |
| 第1順位 | 子 | あり(再代襲も) |
| 第2順位 | 父母、祖父母 | なし |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | あり(再代襲なし) |
各順位の解説
第1順位:子
子どもがいれば子が相続人となり、既に死亡している場合は孫やひ孫が代襲相続します。配偶者がいる場合、配偶者と子で1/2ずつ、子が複数いればその間で均等に分けます。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
子がいない場合、父母や祖父母が相続人になります。配偶者がいると配偶者が2/3、尊属が1/3を分け合います。
第3順位:兄弟姉妹
第1・第2順位に該当者がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、それ以上の代襲(再代襲)は認められていません。
遺言がある場合の扱い
被相続人が遺言書を作成しており、それが有効と認められた場合、相続は原則としてその遺言の内容に従って行われます。
つまり、遺言書に財産を受け取る人が明記されていれば、その人が指定された通りに財産を取得し、法定相続人の順位や割合は適用されません。
ただし、遺言によってすべての財産を法定相続人以外に与えると、配偶者や家族の生活に深刻な影響が出ることがあります。
そこで民法では、特定の法定相続人に対して「遺留分」という最低限の取り分を保障する制度を設けています。
遺留分が認められるのは、配偶者、子や孫などの直系卑属、そして父母や祖父母などの直系尊属に限られており、兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺留分の割合は、原則として法定相続分の半分、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1とされています。
遺産分割協議と法定相続分の関係
民法では、各相続人が受け取る遺産の割合を「法定相続分」として定めています。
この割合は、配偶者の有無によって大きく異なります。
配偶者がいない場合、相続人が複数いれば、その人数で遺産を均等に分けるのが原則です。
一方、配偶者がいる場合は、配偶者とその他の相続人との関係に応じて分配割合が決まります(詳細は前述の表をご参照ください)。
ただし、法定相続分はあくまで“目安”にすぎません。
被相続人が遺言を残していない場合でも、相続人全員の合意があれば「遺産分割協議」によって自由に分け方を決めることができます。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の配分について話し合い、合意形成を図る手続きです。この協議で合意した内容は、法定相続分よりも優先されます。つまり、法律の定めにとらわれず、相続人同士の合意によって柔軟に遺産を分けることができるのです。
まとめ~子なし夫婦は特に相続対策を~
子どものいない夫婦では、配偶者だけでなく親族が相続人となる可能性が高く、思わぬ相続トラブルの原因にもなります。
自分の財産を希望どおりに引き継がせたい場合や、配偶者を守りたい場合には、遺言の作成や生前の相続対策が重要です。遺言や養子縁組、寄付の活用なども検討しましょう。
弊所には生前対策の実績が多数ございます!お気軽にお問い合わせください。