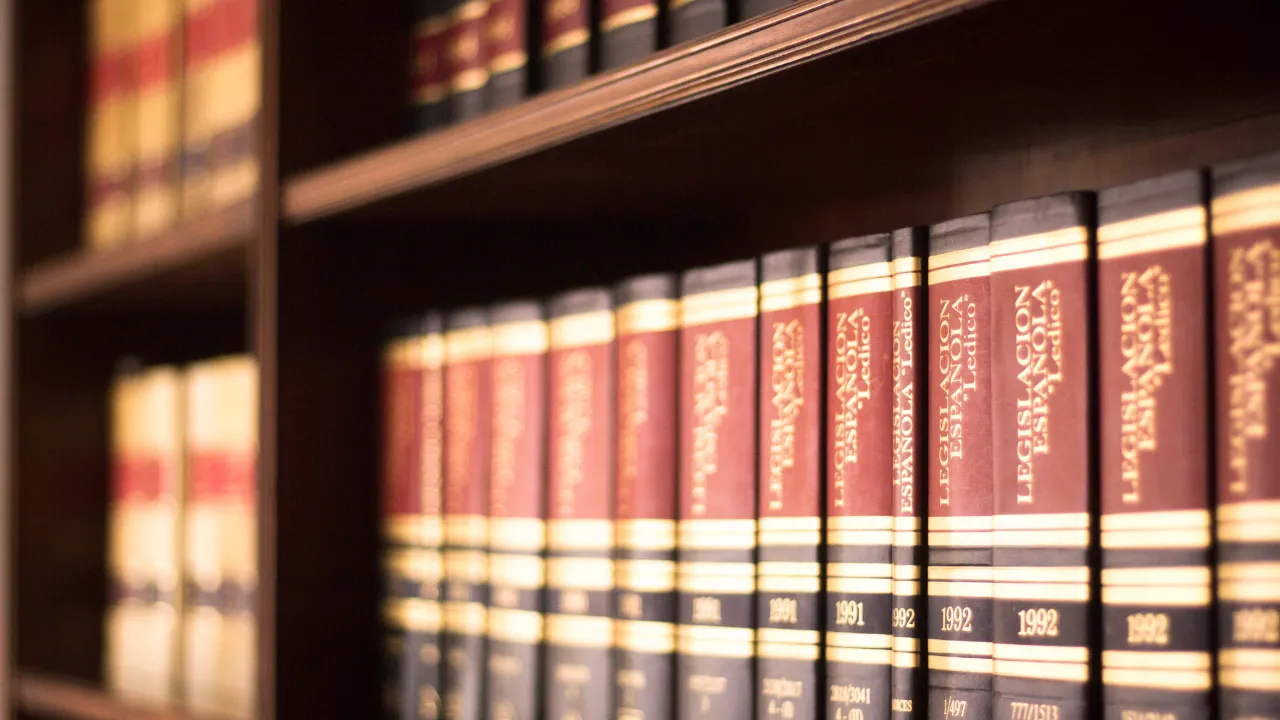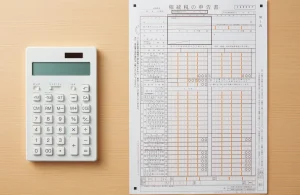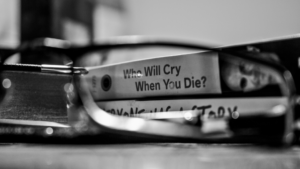【寄与分】遺言書がない中で、介護に尽力した依頼者の相続分を確保したケース
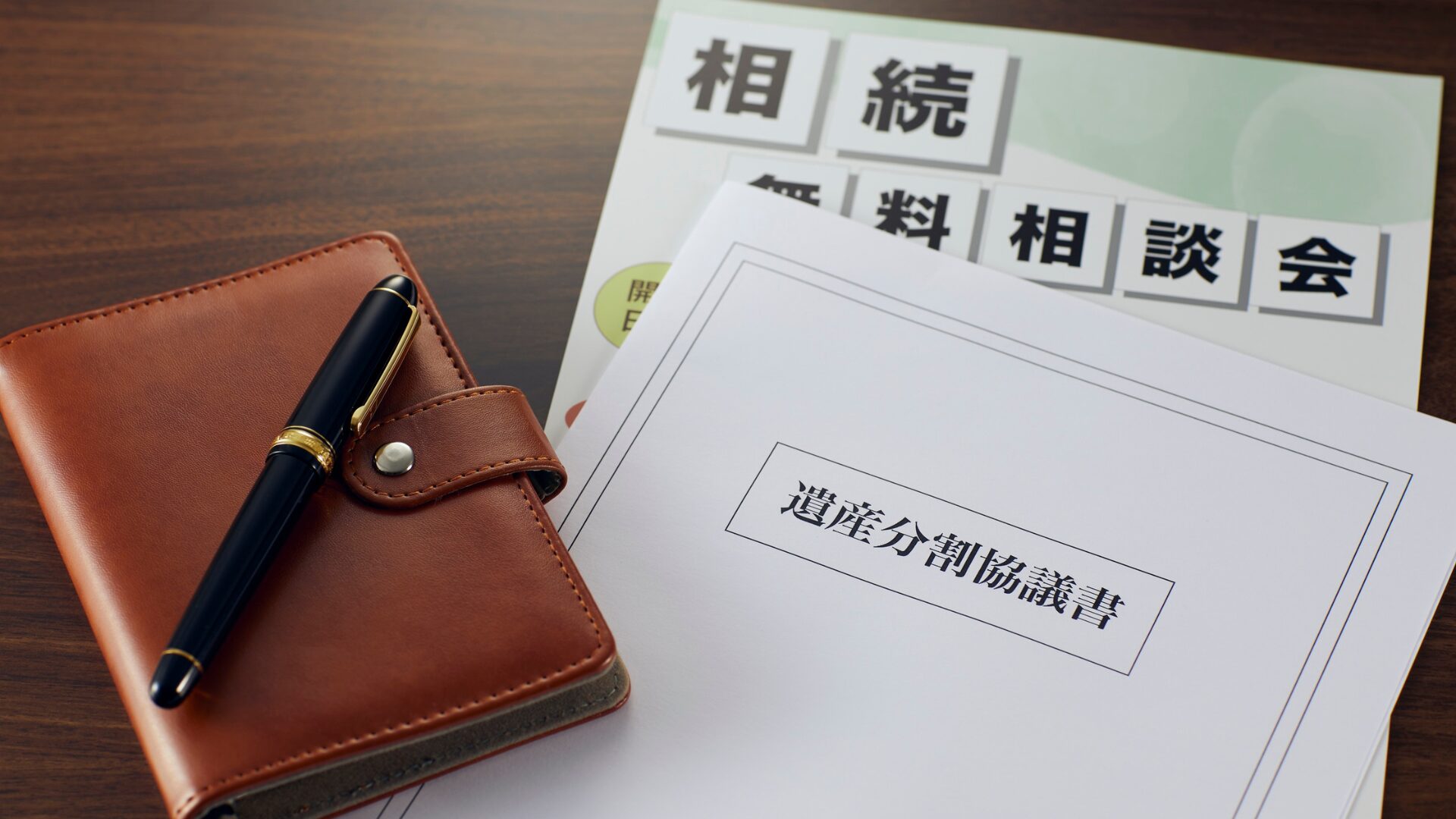
クライアント情報
日野市在住/60歳男性
問題となっていた事柄
依頼者の母が亡くなり、相続が発生しました。相続人は依頼者と、依頼者の姪(故人の孫)の2名です。依頼者は母と同居し、日常的な介護や身の回りの世話を一人で担ってきました。生前、母から「財産はすべてあなたに渡したい」と口頭で言われていたものの、正式な遺言書は作成されないまま亡くなってしまいました。
相手方である姪は、現在服役中であり、直接の交渉は困難な状況です。それにもかかわらず、相手方は「できるだけ多くの遺産を取得したい」との意向を示しており、話し合いも進まず、依頼者は法的手続を通じた解決を求めてご相談にいらっしゃいました。
争点
本件の主な争点は、遺言書がない中で、依頼者がどの程度の相続分を確保できるかという点でした。法定相続分では依頼者と姪が各2分の1ずつとなりますが、依頼者は生前の介護という「特別の寄与」があったことから、寄与分の主張が重要な法的ポイントとなりました。
弁護士が介入した結果
当職は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所を通じた交渉を開始しました。調停では、依頼者が母の介護を長年にわたり一人で担ってきた事実を丁寧に主張し、関係資料(介護記録、同居の状況、医療機関の通院記録など)を提出しました。
また、以下の最高裁判例を根拠に、依頼者の寄与分が相続分に反映されるべきであると主張しました
最高裁平成16年4月20日判決(民集58巻4号1107頁)
被相続人の療養看護について、特別の寄与があった相続人には、寄与分として相続分を増加させることができると判示。
この判例に基づき、依頼者の長期間の介護は「特別の寄与」に該当すると認められる可能性が高いと裁判所も判断し、現在、依頼者が法定相続分を上回る内容での調停成立が見込まれている状況です。
遺言書がなかったことで一時は不安に感じていた依頼者も、「法律的に正当に主張する方法がある」ことを知り、安心して手続きを進められるようになりました。